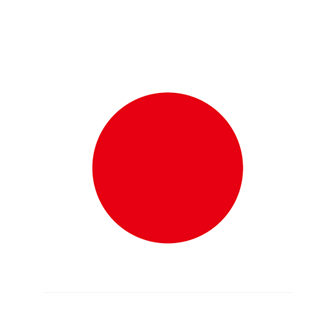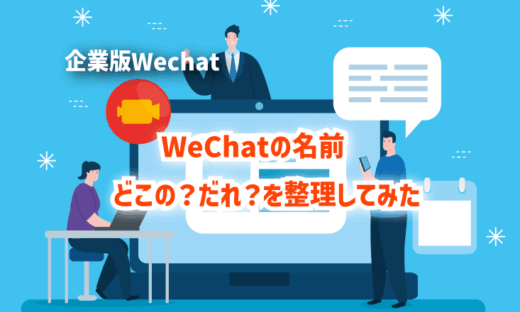顧客はWeChatのままでOK ― 企業版WeChat(WeCom)で広がる中国BtoB営業の新常識

中国におけるグループウェア(OAシステム)市場は、2000年初頭のPC全盛期に登場した泛微(Weaver)が長らく独占していました。しかし、スマホの普及に伴い、2015年にアリババが「钉钉(DingTalk)」、2016年にテンセントが「企業版WeChat(WeCom)」をリリースし、スマホ主体のグループウェア市場は一気に競争が過熱しました。
その後も、用友や金蝶といった大手会計ソフト企業、さらにはTikTokで知られるバイトダンスなども次々と参入し、まさに群雄割拠の状況となりました。
そして本記事執筆時点(2025年現在)では、各社がそれぞれ独自の数値を示し、好調さをアピールしていますが、実感としてはテンセントの企業版WeChat(WeCom)の一人勝ちでほぼ決着したと考えています。
少なくともBtoB営業組織を持つ企業においては、日系・中国系を問わず、
- 社内連絡や勤怠管理 → 企業版WeChat(WeCom)
- 見積・案件管理 → kintoneなどのSFA
という組み合わせで運用するケースが非常に多いです。
その市場シェアを決定づけた最大の要因が、今回ご紹介する「外部連絡先機能」だと私は考えています。本稿では、この機能の概要やできることを紹介しつつ、導入を検討する際によくある質問にも触れていきます。
Contents
外部連絡先機能とは
2020年10月にリリースされた機能で、顧客・仕入先・協力業者など企業外の人と情報共有ができる仕組みです。具体的には、チャット、ダイレクトメッセージ、ファイル共有、アンケート収集などが可能です。
これだけを見ると、技術的には他社も容易に真似できそうに思えます。しかし、テンセントには他社にない最大の強みがありました。
それは、中国国内で生活インフラ化している「WeChat」とのシームレスな連携です。
企業版WeChat(WeCom)の外部連絡先は、
- 社内ユーザー
- 他社の企業版WeChat(WeCom)ユーザー
- そして通常のWeChatユーザー
を対象にできるため、利便性の面で圧倒的優位性を確立しました。
一方、他社が提供する「外部連絡先機能」は、同じグループウェアを関係者にもインストールしてもらわないと成り立ちません。日本で言えばSlackやChatwork、LINE WORKSがこれにあたりますが、関係先の立場や所属組織の方針によって導入が制限され、結果的に浸透しにくいのが実情です。
対して中国では、仕事にWeChatを使うのは当たり前という商習慣があり、企業が企業版Wechat(WeCom)を導入しても、相手(顧客や仕入先)は従来どおりWeChatでやりとりできます。そのため、業務上まったく支障がないのです。
実際によくある質問に、「相手も企業版WeChat(WeCom)を導入していないと使えないのでは?」というものがありますが、上述通り、答えはNoであり、相手は通常のWeChatで問題なく利用できますのでご安心ください。
企業版WeChat(WeCom)導入で得られる主なメリット
連絡先を会社資産として一元管理
WeChatはあくまでもプライベート利用のためのツールです。もし、仕事中にある従業員が誰か顧客とつながって、その後、退社した場合、その顧客の連絡先は辞めた従業員しか持っていないため、会社としてフォローが出来なくなります。そのため、顧客を丸ごと持ってかれてしまうということが日常茶飯事に起こります。
一方、企業版WeChat(Wecom)には、退職時に、「担当者引き継ぎ機能」があるため、少なくとも連絡ができないということは無くなります。つまり顧客連絡先を会社の資産として持つことができます。
実は、この仕組みが、現場の人間からの反発で企業版WeChat(Wecom)を導入しない一番の理由になるのですが、最近では、中国の国営企業を始め、どんどん導入が進んでいるため、時間が経過するにつれて、その反発は少なくなるのではないか?と考えております。そして、いずれ、WeChatしか使ってない会社は逆に怪しい会社という認知になるかもしれません(あくまでも想像ですが)。
というのは、WeChatでの業務やりとりは、日本でいうと個人のgmailやyahooメールを使って仕事上のやりとりをしているのと同じであり、本来は、企業にとっても情報管理という観点では望ましくないやり方です。しかし、今まではWeChatのお手軽さに匹敵する代替手段が無かったため、企業としても本当は望ましくないとわかりつつ、見て見ぬふりをしていたのですが、現在は企業版WeChat(WeCom)で相手に負担をかけずに出来るようになったので、次々と導入が進んでいると考えております。実際、弊社の問い合わせも増えております。
会社として使わせたいが、現場のメンバーが反発した場合にどうすればいいですか?という質問もよくいただくのですが、この質問に関しては、会社の状況に合わせながら慎重に進め方を検討する必要があります。
その中でも大きく二つの進め方があります。
一つ目は、情報統制の観点から本社の指示に基づき、外部との情報やり取りについてログ取得を義務化し、現地法人に対して「メール」か「企業版WeChat(WeCom)」のいずれかを選択させる形で、半ば強制的に導入を進める方法です。
もう一つは、日々のコミュニケーション自体は従来どおりWeChatを使っても構わないとしつつ、まずは連絡先の交換を企業版WeChat(WeCom)で行い、つながった人数を営業KPIとして定義することで小さく始める方法です。そこから利用に慣れていくことで、徐々にコミュニケーションそのものも企業版WeChat(WeCom)に移行していくという、ボトムアップ的な進め方が考えられます。
上述のように今は反発はおそらく過渡期であり、数年もすれば常識になるのではないか?と淡い期待を持っております。
チャットのログ管理
メールでBCCを残すように、企業版WeChat(WeCom)でもチャットログを全て記録できる仕組みを提供しています。これにより、情報漏洩発生時の調査、承認外の見積提出などの証跡確認が可能になり、コンプライアンス強化につながります。
1to1ダイレクト配信
中国でも情報配信をして顧客と接点を持ち続けるということは非常に重視されている一方で、中国ではメール配信をしても全くといって良いほど効果がありません。そこで企業版WeChat(Wecom)の外部連絡先を利用していれば、情報を1 to 1で配信することができます。配信操作を代表者が行うところはメール配信と同じですが、メールと違い、顧客は代表メールアドレスからの機械的な配信ではなく、つながった連絡先からの「普通のチャット」として受け取るため、反応率が非常に高いのが特徴です。
展示会・イベントでのリード獲得とフォローアップ
本件の詳細については別記事で改めてご紹介しますが、中国では名刺を持っている人の割合が非常に少ないのが実情です。
そのため、展示会などのイベントでは、接客担当者が個人のWeChatで来場者とつながるケースが多く、さらに繋がったとしてもWeChat名がニックネームの場合が多いため、誰が誰なのか特定できません。結果として、組織として「イベントで新規に何人と連絡先を獲得できたのか」「その後のフォロー営業で何件の案件に繋がったのか」といった情報を把握できない状況が生じていました。
しかし、この「外部連絡先機能」と「アンケート収集機能」を組み合わせることで、集客・アンケート・フォローアップを組織的に管理・実行できるようになります。
AIによるレポート効率化
企業版WeChat(WeCom)ではチャットのやりとりを期間指定しAIが自動で要約してくれるため、営業日報やレポート作成が効率化できます。
まとめ
中国では、企業版WeChat(WeCom)の「外部連絡先機能」が広く浸透したことで、BtoB営業のスタイルが日本とは異なる独自の発展を遂げています。
中国でビジネスを展開する企業にとっては、現地の商習慣に沿ったコミュニケーション基盤を持つことが重要です。本記事が、導入を検討される皆様の参考になれば幸いです。