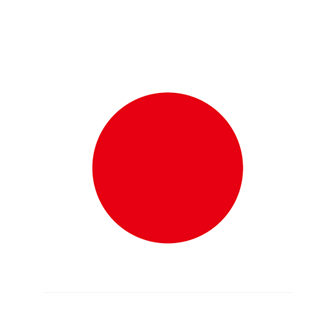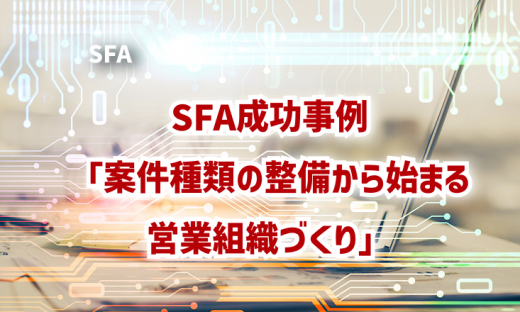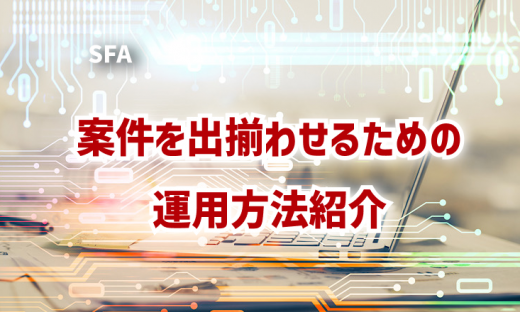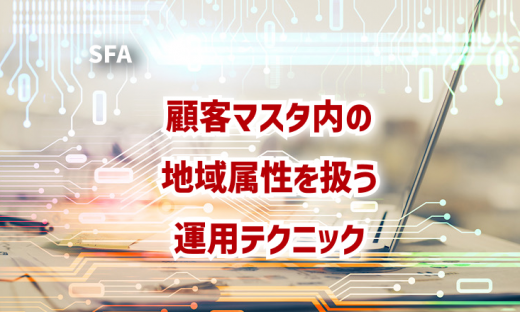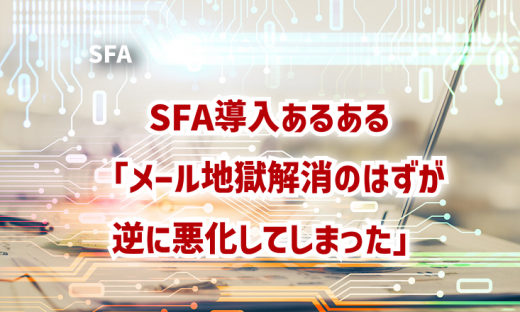テンプレートはあくまで土台。SFA導入で大切な視点とは?
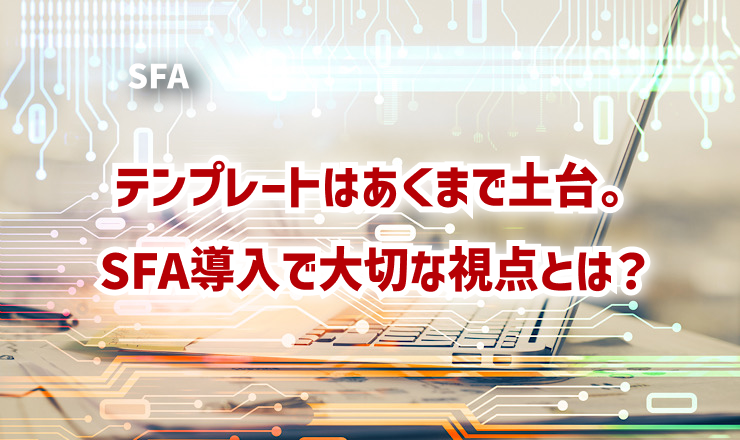
SFA導入を検討する際、ベンダーからほぼ必ず提案されるのが、「○○別テンプレート」(業界別、業態別など)です。
特に欧米系のベンダーでは「ベストプラクティス」と呼ばれることもあります。導入経験がない企業が、こうしたテンプレートをベースにしたデモを見ると、「これならすぐにSFAを使い始められそう」「営業活動がすぐに見える化・効率化されそう」と期待してしまいがちです。
しかし、実際にSFAを導入した経験のある企業の多くは、「テンプレートはそこまで期待するものではなかった」と感じているのが実情です。
なぜこのようなギャップが生まれるのでしょうか?
この記事では、その原因をいくつかご紹介しながら、「テンプレートはあくまで出発点(=土台)であり、完成品ではない」という前提をふまえて、SFAの導入やリプレイスを進めていただければと思います。
根本原因は、売り手(ベンダー)と買い手(自社)の立場の違い
SFA導入を検討する際、提案してくるベンダーには大きく2つのタイプがあります。
ひとつはSFAを自社で開発している「メーカー」、もうひとつはそれを取り扱うSier(システムインテグレーター)、コンサル会社、商社などの「販売パートナー」です。
当然ながら、メーカーが最も重視しているのは「SFAの利用料収益」です。導入支援や初期設定といったサービスは、その利用料を得るための“手段”であり、補足的な利益であることが多いのが実情です。
その中で、テンプレートの提供には、2つの目的があります。
ひとつは、「SFAの運用ノウハウがない企業でも、導入しやすくする」ため。もうひとつは、「なるべく効率よく利用料収益を得る」ための仕組みとしての側面です。
この“テンプレートの二面性”が、買い手側の過剰な期待と、実際に使ってみたときのギャップを生み出す要因になっています。
次の段落では、テンプレートの特徴と、それがどうしてギャップにつながるのかについて、具体的にご紹介していきます。
要件濃淡のギャップ
テンプレートは、当然ながら多くの企業で使えるように「汎用的」に作られています。これは、メーカーにとってどの企業にも適用できる“最大公約数的な要件”でなければ、テンプレートとして意味を持たないためです。
たとえば「見積機能」があるかどうかでいえば、テンプレートには一応「ある」と言えるものの、価格計算の仕組みなどは非常にシンプルに作られているケースが多くあります。単価を手入力するだけの仕様など、いわば“要件の濃淡”でいうところの“淡い”部分に合わせて作られているのです。
そのため、実際の導入フェーズに入ると、自社の具体的な業務との間にギャップが見えてきます。
このギャップに対しては、「運用でカバーする」「標準機能の範囲内で何とか工夫する」「二次開発で補う」などの判断が必要になり、特に開発が必要な場合は当然ながら追加コストが発生します。
データのギャップ
テンプレートを使ったデモでは、決裁者から「これが欲しかったんだよ!」と思ってもらえるようにサンプルデータが非常に丁寧に作りこまれています。
たとえば、経営ダッシュボードでは営業状況があらゆる角度・粒度でビジュアル的に分かりやすく表示され、特定の顧客に関しても、定性情報・過去の取引履歴・接触履歴などが整理され、まるで“営業カルテ”のように見える構成になっています。
しかし、これはあくまでデモ用に最適化された「理想的なデータ」が入っているからこそ成り立つ世界です。
実際の運用では、たとえば「顧客規模別の収益レポート」を実現するために、顧客規模の情報を継続的にメンテナンスする仕組みや、その担当者の割り当てが必要になります。
また、過去の取引情報を表示するには、既存の業務システムとのデータ連携や、項目・形式の違いを吸収するための運用設計・開発が不可欠です。
つまり、必要なデータが整っていなければ、どれだけ見た目が優れたテンプレートでも、期待したアウトプットは得られないということです。
組織のギャップ
テンプレートを使ったSFAのデモは、先に述べたような「理想的なデータ」だけでなく、実は「理想的な組織」を前提に作られていることが多くあります。
ここで言う「理想的な組織」とは、以下のような状態を指します:
- データ(事実情報)をもとに意思決定・業務遂行・評価が行われている
- 情報を個人で抱え込まず、組織として積極的に共有する風土が根づいている
こうした組織であれば、SFAのテンプレートがすんなりフィットし、スムーズに活用が進みます。
しかし現実には、「個々の営業担当が情報を閉じた状態で持っている」「データが整理されておらず、正確な現状把握ができていない」といった、“非理想的な組織”がSFA導入を検討するケースがほとんどです。
つまり、「理想的な組織」になるためにSFAを導入しようとしているのに、テンプレートはすでに“理想が実現している前提”で作られている。ここに大きなギャップが生まれます。
加えて、メーカーやベンダーの役割はあくまで「ツールを提供すること」であり、営業メンバーが自発的に情報を入力し、マネージャーがチェック・共有するような組織文化の改革までは、サービスの対象外であることが多いのです。
このギャップを理解せずに導入を進めると、「なぜ入力が定着しないのか?」「なぜレポートが機能しないのか?」といった課題に直面することになります。
まとめ
以上、大きく3つのギャップについてご紹介しました。
これらのギャップを埋めるために、「販売パートナー」はコンサルティングを含めた支援サービスを提供しています。ただし、当然ながらその分の費用が発生することも理解しておく必要があります。
SFA導入を検討する際は、「テンプレートさえあればすぐに使える」という考えは一度捨てましょう。テンプレートはあくまで“たたき台”であり、自社に合わせて調整・整備していくものです。
そのうえで、自社の状況(人的リソース、現場のITリテラシー、組織の風土)を踏まえ、
- メーカーから直接導入するのか?
- 販売パートナーを通じて導入するのか?
- どのような支援体制・強みを持つ販売パートナーを選ぶべきか?
といった視点で慎重に検討されることをおすすめします。